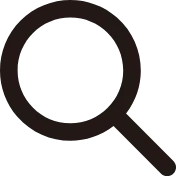SEARCH
空の検索で70件の結果が見つかりました。
- オーダーメイド門扉とは?既製品との違い・費用・事例を徹底解説
住まいの第一印象を大きく左右する「門扉」。既製品ではしっくりこない、建物の雰囲気に合わないと感じたことはありませんか? とくに輸入住宅やデザイン性の高い住宅では、 門扉の存在感がエントランス全体の完成度を左右 します。そこで注目されているのが、オーダーメイド門扉(カスタム門扉)です。 この記事では、 オーダーメイド門扉とは何か 既製品との違い 気になる価格・費用感 実際の施工事例イメージ について、初めて検討する方にも分かりやすく解説します。 オーダーメイド門扉とは? オーダーメイド門扉とは、 設置場所・デザイン・要望に合わせて一から製作する門扉 のことです。 既製品のように決まったサイズやデザインではなく、 開口寸法 高さ デザイン・装飾 曲線や意匠 などを自由に設計できるのが最大の特徴です。特に、 輸入住宅 海外風デザインの外観 重厚感のあるエントランス を目指す場合、当社のオーダーメイド門扉は非常に相性が良い選択肢といえます。 オーダーメイド門扉と既製品門扉の違い オーダーメイド門扉と既製品門扉には、明確な違いがあります。 1.デザインの自由度 既製品は、メーカーが用意したデザイン・装飾の中から選ぶ形になります。一方、オーダーメイド門扉は、 曲線・装飾・格子デザインなども自由に設計可能 。建物の雰囲気に合わせた唯一無二の門扉が実現します。 2.サイズ対応力 敷地条件によっては、既製サイズでは「微妙に幅が合わない」「高さが足りない」といったケースも少なくありません。オーダーメイドなら、 現地寸法に合わせたジャストサイズ で製作でき、美しい納まりを実現できます。 3.外構全体との調和 門扉単体ではなく、 「建物外観」「アプローチ」とのバランスまで考慮 できるのがオーダーメイドの強みです。 オーダーメイド門扉はどんな人に向いている? オーダーメイド門扉は、次のような方におすすめです。 輸入住宅・海外住宅風の外観にこだわりたい 既製品ではデザインが物足りない エントランスに重厚感・存在感を出したい 狭小地や高低差のある敷地に対応したい 門扉と手すりを統一デザインで作りたい 「外構は妥協したくない」「家の顔を大切にしたい」という方ほど、オーダーメイドの価値を実感できます。 オーダーメイド門扉の価格・費用相場はいくら? もっとも気になるのが価格ではないでしょうか。 オーダーメイド門扉の価格は、 サイズ デザインの複雑さ 装飾量 材質によって大きく変動します。 参考価格の目安 門扉本体: 約70万円前後〜 手すり: 約7万円前後〜 施工費・運搬費:別途 実際の施工例では、 門扉+手すり+工事費込みで約100万円前後 となるケースが見られます。 単純に「高い・安い」ではなく、 デザイン性・耐久性・満足度を含めたコストパフォーマンス で考えることが重要です。 施工事例から見るオーダーメイド門扉の魅力 オーダーメイド門扉の魅力は、写真や施工事例を見ると一目瞭然です。 曲線を活かした優雅なデザイン 建物と一体化した重厚な存在感 海外住宅のような雰囲気 既製品では表現しきれない「空気感」までデザインできるのが、オーダーメイドならではの魅力です。 門扉と手すりを同一デザインで製作することで、エントランス全体に統一感が生まれ、ワンランク上の外構デザインが完成します。 キャン’エンタープライゼズのオーダーメイド門扉の特徴 当社では、海外住宅風デザインを得意とした 完全オーダーメイドの門扉・手すり を製作しています。 サイズ・デザイン自由設計 曲線・装飾を活かした重厚感ある意匠 門扉のみ、手すりのみの注文も可能 建物とのバランスを重視した提案 東京・神奈川・千葉を中心に施工対応しており、その他エリアについても随時ご相談が可能です。 よくある質問(FAQ) 納期はどのくらいかかりますか? デザイン確定後、製造開始から約1.5〜3ヶ月程度が目安です。 施工込みでの注文は可能ですか? 可能です。施工エリアは東京・神奈川・千葉を中心に対応しています。その他エリアも拡大中です。 理想のエントランスを、オーダーメイド門扉で 門扉は、住まいの「顔」となる重要な要素です。既製品では叶えられない理想のデザインや存在感を求めるなら、オーダーメイド門扉という選択は大きな価値をもたらします。 海外住宅のような重厚感あるエントランスを実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。 手すり施工事例 手すりも併せてぜひご検討ください! 「この価格でどこまでできるのか知りたい」「自分の家に合うか相談したい」 という方は、お気軽にデザイン相談をご利用ください。
- 庭に癒しの炎を。日本製ファイヤーピットで始めるおうちアウトドア
ファイヤーピットとは? 近年、庭やテラスといった屋外空間をもっと豊かに楽しむスタイルとして注目されている「ファイヤーピット」。 ファイヤーピットとは、屋外で焚き火を安全に楽しむための炉(ろ)や囲炉裏のような設備のことで、直訳すると「火の囲い」を意味します。 元々はアメリカの住宅や別荘などで広く親しまれているアイテムでしたが、日本でも「庭キャンプ」や「おうちアウトドア」ブームの高まりとともに、広い庭を持つご家庭や別荘オーナーを中心に導入が進んでいます。 自宅の庭で広がる新しいアウトドア時間 「キャンプ場に行かなくても、焚き火のあたたかさや癒しを楽しみたい」 そんな思いを叶えてくれるのが、ファイヤーピットです。 火の揺らめきを眺めながら語らうひとときは、家族や友人とのコミュニケーションをより深めてくれます。 また、日が沈んだあとでも温かみを感じられるため、春秋の夕暮れや冬の夜にも重宝します。 庭にファイヤーピットがあるだけで、日常の空間が一変。 アウトドアチェアを並べてリラックスしたり、温かい飲み物を片手に本を読んだり、そんな特別な時間が自宅で味わえるのです。 ファイヤーピットの魅力と使い方 ファイヤーピットの魅力は、何といってもその多機能性。 焚き火台としての使用はもちろん、五徳や焼き網を使えば簡単な料理も楽しめます。ウィンナーやマシュマロを焼く、スキレットでアヒージョを作る、そんなカジュアルな「庭ごはん」もおすすめです。 また、インテリアとしても魅力的で、自然石調の意匠を持つ製品なら、昼間でもガーデン空間のアクセントとして映えます。 夜には、ゆらゆらと揺れる炎が演出する非日常の世界へ誘ってくれます。 煙突や屋根がない分、開放感があり、360度どこからでも焚き火を囲める点もファイヤーピットならでは。 リビングからそのまま外へとつながるような空間を目指す「アウトドアリビング」の構成要素としても、ファイヤーピットはぴったりです。 選ぶなら日本製・高品質・デザイン重視 屋外に設置するものだからこそ、安心できる品質であることはとても大切です。 御社製のファイヤーピットは、日本国内で丁寧に製造されており、耐久性・安全性に優れた構造となっています。 また、見た目にもこだわりたい方にとっては、無骨すぎないデザイン性も重要なポイント。 天然石を思わせる素材感や色合いは、洋風の庭にも和モダンな外構にも自然になじみ、景観を引き立てます。 「火を囲む」という原始的な体験を、現代のライフスタイルに美しく取り入れる。 その発想を具現化したプロダクトが、御社のファイヤーピットです。 サイズは2種類展開 サイズ: W: ≒1120×H: 305×D ≒1120×mm サイズ: W: ≒814×H: 305×D ≒814×mm より多くのシーンで使っていただけるよう、限られたスペースにも対応できる“小サイズ”と、ゆったり焚き火を楽しめる“大サイズ”の2種類を展開。場所や人数に応じて最適な一台をお選びいただけます。 当社ファイヤーピット製品の特徴 当社オリジナルのファイヤーピットは、次のような特徴を持っています: 日本製の安心品質 工具不要で誰でも簡単に組立可能 最短10分で設置が完了するDIY仕様 モジュール構造によるコンパクト梱包 カラーバリエーションはホワイトとグレーの2色展開 周囲の庭石やタイルとも調和しやすい自然な外観 現場での加工や特別な技術は不要。説明書通りにパーツを積み重ねるだけで、美しい円形の炉が完成します。 DIY初心者の方でも、動画や写真を見ながら簡単に施工できるよう設計されています。 実際の設置例と使い方アイデア 例えば、広めのウッドデッキの中央にファイヤーピットを配置すれば、リビングからそのままつながるアウトドア空間が完成。 芝生の上に*直接設置しても、周囲の自然素材と調和し、アウトドアリゾートのような雰囲気を演出できます。+ *直置不可、施工要領確認のうえ: 施工要領 夜には、LED照明と組み合わせることで幻想的なムードが生まれます。 また、ガーデンチェアを囲むように配置すれば、キャンプファイヤーのような憩いの場に早変わり。 焚き火好きの方だけでなく、「非日常の癒し空間を日常に取り入れたい」と考えるすべての方におすすめの設計です。 まとめ:ファイヤーピットで庭に特別な時間を 屋外で火を囲むという体験には、人を惹きつける不思議な力があります。 安心・安全・美しさ・手軽さ、そのすべてを兼ね備えた当社のファイヤーピットなら、あなたの庭に新しい価値が生まれます。 アウトドアが好きな方はもちろん、これからお庭での過ごし方をもっと充実させたいという方にも、ぜひご検討いただきたいアイテムです。 静かに炎が揺れる時間。日常の延長にある非日常。 ファイヤーピットで、そんな贅沢なひとときを暮らしに取り入れてみませんか?
- 冬期休暇のお知らせ
誠に勝手ながら、弊社は下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。 2025/12/27(土)~ 2026/1/4(日) ※年末は12月26日(金)まで、年明けは1月5日(月)より通常営業いたします。 今後とも一層のご愛顧の程、宜しくお願い致します。
- ファイヤーピットのよくある質問(FAQ)|庭で安全に焚き火を楽しむための基礎知識
※本記事の内容は2025年現在、当社が独自に調査・確認した情報をもとに構成しています。地域の条例や運用状況は変更される可能性があるため、実際のご使用にあたっては必ず自治体や消防署にご確認ください。当社では使用に関する責任は負いかねますので、予めご了承ください。 近年、アウトドアリビングや庭キャンプの人気が高まる中、自宅の庭にファイヤーピット(焚き火台)を設置したいという声が増えています。しかし、「そもそも自宅の庭で焚き火ってしていいの?」「BBQはOKでも焚き火はNGなの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では、首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を中心に、個人宅でファイヤーピットや焚き火を使用する際の法的・条例的な制限について、当社が調査した内容を、一次情報ソースを交えて詳しく解説します。 自宅の庭での焚き火やBBQは禁止? 結論から言えば、 私有地で焚き火やBBQを行うこと自体は、法律で明確に禁止されているわけではありません。 環境省によれば、廃棄物処理法に基づく「野外焼却」は原則禁止ですが、以下のように例外が設けられています。 「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの」(廃棄物処理法施行令第14条) つまり、家庭での焚き火やバーベキューは「軽微な焼却」とみなされれば違法ではありません。 ただし、煙や臭い、火の粉などによって近隣住民へ迷惑をかけた場合、行政指導や通報の対象となる可能性があります。環境省の『野外焼却(いわゆる野焼き)について』でも、次のように指摘されています: 「周囲への影響が著しい場合には、たとえ例外として認められる焼却行為であっても指導の対象となる場合があります」 (出典:環境省『野外焼却(いわゆる野焼き)について』 https://www.env.go.jp/recycle/yaki_faq/) 特に住宅密集地では、たとえ小規模であっても煙や火が見えることで”火災”と誤解され、通報されることがあります。 また、マンションやアパートの場合は、ベランダでの火気使用が管理規約で禁止されているケースが多く、たとえ炭火やガスでも使用できない場合があります。 法律と地域条例の違い:首都圏の事例 ● 東京都 東京都は全国的にも最も厳しい環境規制を行っており、都の「環境確保条例」によって以下のように定められています: 「何人も、廃棄物その他の物を屋外で焼却してはならない」(東京都環境確保条例 第126条) 焚き火やバーベキューも、原則としてはこの「屋外焼却」に含まれる可能性があり、例外対象として認められるのは「区市町村が必要と認める農業行為」「どんど焼きなど伝統行事」などに限られています。 参考:東京都 環境局「屋外での焼却行為について」 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/air/jorei/jorei_sonota ● 神奈川県 神奈川県では、廃棄物処理法の枠組みを踏まえつつ、生活上必要なバーベキュー・キャンプファイヤー等については例外として黙認されています。 「軽微な焼却行為(バーベキュー、キャンプファイヤー、落ち葉焚き等)は、常識の範囲内で行われる限り、原則禁止の対象外」(神奈川県 環境農政局「野外焼却(野焼き)の禁止」) 参考:神奈川県「野外焼却(野焼き)の禁止」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ph7/cnt/f219/p591169.html ただし、近隣から苦情が寄せられた場合は、現地調査の上、指導の対象となる可能性があります。 ● 千葉県 千葉県でも原則として屋外焼却は禁じられていますが、「日常生活に伴う軽微な焼却行為(たき火、キャンプファイヤー、バーベキュー等)」については例外扱いとされており、煙や臭いにより生活環境に支障を与えた場合は行政指導の対象となります。 参考:千葉県「野外焼却(野焼き)について」 https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/hanamigawa-inage/noyakinokinnsi.html ● 埼玉県 埼玉県でも、焚き火やBBQは「日常生活に伴う軽微な焼却行為」として、条例上禁止の対象外とされるケースが多いですが、生活環境の保全に反すると判断されれば指導の対象です。 「落ち葉焚きやキャンプファイヤー、バーベキュー等は、通常生活で行われる軽微な焼却として例外とされます」 参考:埼玉県「野外焼却の禁止について」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/kurashi/gomi/sangyo/noyakikinshi.html 焚き火とBBQの違い 法律上は、焚き火もBBQも同様に「軽微な焼却」に含まれますが、実際の印象は異なります。 BBQは調理行為とみなされ、日中の短時間で終わることが多く、近隣から理解を得られやすい焚き火は炎が大きく、夜間の使用や煙・火の粉の発生も多いため、心理的な通報リスクが高い さらに、焚き火の場合、もし「落ち葉や廃材」を燃やしていれば廃棄物処理法に違反する可能性があります。燃やすのは市販の薪や炭のみにし、ゴミや剪定枝などは決して燃やさないよう注意が必要です。 ガス・電気グリルはOK? ガスグリルや電気調理器は「焼却」ではないため、廃棄物処理法の対象にはなりません。そのため煙が出にくい、近隣への配慮がしやすいという点で有利です。 ただし、火気にあたるためマンションのベランダなどでは規約違反になる場合があります。また、通電時の事故や延長コードによるトラッキング火災にも注意が必要です。 消防法・軽犯罪法との関係 火気使用が原因で火災が発生したり、その危険がある場合には、消防法や軽犯罪法にも関わります。 「相当の注意をしないで、火をたいたり、またはたばこを投げ捨てた者」は拘留または科料に処される(軽犯罪法第1条第9号) また、消防法では以下のように定められています: 「消防署長等は火災の予防上必要があると認めるときは、火の使用の制限その他必要な措置を講ずることができる」(消防法 第16条の3) つまり、近隣から通報された場合には、消防署が現地で指導・中止命令を出す可能性があります。 参考:総務省消防庁「火災予防条例・火気使用に関するQ&A」 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/knowledge/faq/ 安全に楽しむための対策 よく乾いた薪や炭など、煙の少ない燃料を使う🪵 風の強い日、乾燥注意報が出ている日を避ける🌪️ 消火器や水バケツを常備する🪣 夜間の使用は避け、20時頃までを目安に終了⏰ 周囲の住宅と距離を取り、建物や木に燃え移らないようにする🏘️ 可能であれば事前に近隣へ一言伝えておく🗣️ まとめ 自宅の庭での焚き火やファイヤーピットの使用は、必ずしも法律違反ではありませんが、条例や近隣との関係性によって、トラブルになる可能性があります。 特に東京都内は規制が厳しく、形式上はNGとされるケースも多く見られます。一方、神奈川・千葉・埼玉では「常識の範囲」であれば黙認される傾向もあり、使用する地域の条例と環境を理解することが大切です。 当社としても、火を安全に・快適に楽しむ屋外空間づくりを応援しています。この記事がファイヤーピットを検討される皆様の参考になれば幸いです。 ※本記事の内容は2025年時点の調査に基づいた一般的な情報であり、法的保証を行うものではありません。最新の情報は、必ず各自治体・管轄消防署にご確認ください。
- 屋外ブラケットライト — 玄関と外壁を格上げする輸入ブラケット5選(CAN2432 / CAN2422 / CAN2421 / CAN2971 / CAN1161)
外観の第一印象を左右する屋外ブラケットライト。 素材や仕上げ、フォルムの違いで家全体の表情は大きく変わります。ここではU.S.A.アンティークの風合いを持つ当社の輸入ブラケットから、 CAN2432-BK/CAN2422-BK/CAN2421-BK/CAN2971-BK/CAN1161-BK の5モデルをピックアップ。 実際の設置イメージとともに、選び方や施工・メンテナンスの注意点まで、導入に役立つ情報をまとめました。 製品紹介 CAN2432-BK(SATIN PLATINUM CLEAR GLASS) サテンプラチナ調の上品なメタリック仕上げとクリアガラスの組合せが特徴。光が柔らかく拡散し、玄関ポーチに落ち着いた高級感を与えます。木製ドアやタイル仕上げの玄関と好相性で、ホテルライクな佇まいを目指す住宅に最適です。屋外仕様・PSE検査クリア。 CAN2422-BK(MATTE BLACK CLEAR GLASS) マットブラックのランタン型シルエット。シャープな黒が白い外壁やレンガの良いアクセントになり、モダンからカントリーまで幅広く対応します。複数灯でリズムよく並べると外構に統一感が生まれます。 CAN2421-BK(MATTE BLACK CLEAR GLASS) 壁付けのスタンダードモデル。伝統的な意匠を残しつつも主張しすぎない万能デザインで、玄関脇の主照明や軒下の補助照明として使いやすい一灯。視覚的な安定感を重視する住宅におすすめです。 CAN2971-BK(MATTE BLACK CLEAR GLASS) 装飾的なクラシックフォルムが魅力のモデル。曲線や細部の意匠が外構にアクセントを加え、庭まわりや門柱に設置するとドラマチックな演出が可能です。夜間の視認性を高める機能面も兼ね備えています。 CAN1161-BK(MATTE BLACK CLEAR GLASS) やや重厚感のあるクラシックフォルムで、住宅全体に落ち着いた高級感を添えるモデル。ポーチ横や門扉脇に設置することで、外観の“重心”をうまくまとめる効果があります。 屋外ブラケットライトの選び方ポイント 仕上げ(色) : マットブラックは幅広い外観に合いやすく、サテンプラチナは品の良さを演出します。 耐候性と素材 : 海辺や雪の多い地域では防錆処理やコーティングの有無を重視。製品が国内規格(PSE等)をクリアしているか確認しましょう。 IP等級(防水) : 直接雨が当たる場所には適切なIP等級の器具を選ぶこと。屋根のある軒下と雨ざらしでは要件が変わります。 電球・調光互換性 : E26などソケット規格、調光対応の有無、LED化の可否を確認。サイズや発熱の問題でシェード内に収まらない場合があるため注意が必要です。 取付強度 : 本体重量があるモデルは取り付け面の補強を検討してください。 設置・メンテナンスのコツ 設置高さ: 玄関ドア横は地上から約160〜180cmを目安に。目線の高さに合わせるとバランスよく見えます。 施工: 電気工事は必ず有資格の電気工事業者に依頼してください。配線やアース処理、支持部の強度確認が重要です。 清掃 : 半年に1回程度、ガラスは中性洗剤で優しく洗浄。金属部分は専用クリーナーで保護膜を保ってください。塩害地域では清掃頻度を上げると長持ちします。 部品管理: 輸入品は廃番や部品欠品のリスクがあるため、替えガラスやパーツの在庫確認を事前に行うことをおすすめします。 施工事例の使い方アイデア 玄関ポーチ(CAN2432) :白タイルや木製ドアと合わせると、夜の来訪者を優しく迎える温かい表情に。 エントランス左右に並べる(CAN2422 / CAN2421) :左右対称に配置して動線を強調、外観にリズム感を出せます。 ガレージ脇(CAN2971 / CAN1161) :クラシックなフォルムで重心をまとめ、外構全体に統一感と高級感をプラス。 最後に、屋外照明はデザイン性だけでなく 安全性・耐候性・施工の確実さ が重要です。写真でのイメージや現場の条件に合わせて最適なモデルを選べるよう、製品ページの寸法や電球規格、IP等級の情報を確認のうえ、工事店とご相談ください。製品選定や施工例のご相談、カタログ・サンプルのご依頼は当社の問い合わせページからお気軽にどうぞ。
- 床タイル意匠へのこだわり
>床タイル Tiles 床タイル 床タイル意匠へのこだわり 床タイルは、同じサイズを並べるだけでなく、異なるサイズを組み合わせたデザイン張りや、アクセントタイルを取り入れることで、空間にリズムと奥行きを生み出します。タイルの組み合わせ次第で、空間の表情がより豊かに変化します。 タイルデザインの基本 7つのセオリー シンメトリー グリッド・オフセット ポイント ダイヤモンド・チェッカー 張りわけ・見切り ボーダーパターン 絵画 1.シンメトリー 2.グリッド・オフセット 3.ポイント 4.ダイヤモンド・チェッカー 5.張りわけ・見切り 6.ボーダーパターン 7.絵画 〜7つのセオリーを応用した多様なデザイン〜 ・シンメトリー ・張り分け ・ダイヤモンド ・チェック ・シンメトリー ・見切り ・ダイヤモンド ・チェック ・シンメトリー ・見切り ・ダイヤモンド ・ポイント
- レンガタイルの表情をつくる「成型方法」の違い
― 当社が提案する、風合いで選ぶレンガタイル ― レンガの表情は成型方法によっても変わる? レンガの魅力の一つは、その一枚一枚に宿る表情の豊かさです。そして、その質感や模様の違いは、どのように「成型」されているかによっても生まれます。当社では、レンガの持つ多彩な風合いを忠実に再現したタイルをラインナップしています。ここでは、代表的な成型方法とそれに近い表情を持つ当社商品をご紹介します。 1. 型押し成型 特徴: 柔らかい粘土を型に詰めて成型する伝統的な製法。 表面には自然な凹凸が残り、 手仕事の温もりとアンティーク感 が感じられます。 焼きムラや微妙な色の違いも味わいのひとつです。 近い表情を持つ当社商品 🧱 CAN’BRIC「Manchester– マンチェスター(MC)」 CAN’BRIC 「MANCHESTER – マンチェスター (MC)」 は、 イギリスの古レンガをモチーフにしたレンガタイルです 。古レンガ特有の欠けやひびなどの、味わい深い質感を忠実に再現し、落ち着きのある風合いに仕上げました。重厚感のある住宅や店舗の壁面仕上げ材として、空間に深みと趣を加えるシリーズです。 MC-1 MC-2 MC-3 MC-5 🧱 CAN’BRIC「England– イングランド(ENG)」 CAN’BRICK 「ENGLAND – イングランド(ENG)」 は、 英国の最もトラディショナルなアンティークレンガをリアルに再現したこだわりの逸品です。ハイグレードな建築・空間表現を求めている方におすすめのレンガタイルです。 ENG-1 ENG-2 ENG-3 🧱 CAN’BRIC「England– イングランド(ENG)」 CAN’BRICK 「Amsterdam – アムステルダム (AM)」 は、全体的にサイズが小さめでボーダー状のデザインが再現できるレンガタイルです。 意図的に再現された欠けなどが、深い陰影が織りなす豊かな表情を生み出しています。 AM-1 AM-2 2. ワイヤーカット成型 特徴: 押し出した粘土を細いワイヤーでカットする製法。 切り口に独特の筋模様が生まれ、光の当たり方で陰影が際立ちます。 無骨でインダストリアルな印象 を好む方に人気です。 ▲ワイヤーの跡が残っている 近い表情を持つ当社商品 🧱 CAN’BRIC「St.James– セントジェームス (SJ)」 CAN’BRIC 「St.James– セントジェームス (SJ)」 は、 英国で最もポピュラーなレンガを再現したレンガタイルです 。古き良き時代の意匠を継承しながらも、なじみやすい色味と風合いは、誰もが感じるレンガの温かみを伝えます。 SJ-1 SJ-3 SJ-5 🧱 CAN’BRIC「Netherland– ネザーランド (NL)」 CAN’BRICK 「Netherlands – ネザーランド(NL)」 は、 細身のオランダレンガを模したレンガタイルです 。自由と花と緑を愛するオランダの風土を反映し、柔らかさと素材感を兼ね備えたその意匠は、空間に瀟洒な雰囲気を醸し出します。 NL-5 NL-6 NL-7 3. ナイフカット成型 特徴: ナイフカットとは押し出した粘土をスチール刃でスライスして形を作る製法。 表面は滑らかで、ワイヤー筋が出ず、下辺に粘土のよれ線が生じやすいのが特徴です。 ワイヤーカットに比べ、より上品で落ち着いた質感のレンガになります。 ▲ナイフにより粘土が下辺によれた跡 近い表情を持つ当社商品 🧱 CAN’BRIC「Texas Crenshaw– テキサスクレンショー (TX)」 CAN’BRICK 「Texas Crenshaw –テキサスクレンショー (TX)」 は、 雄大なアメリカの風土と洗練とを融合したレンガタイルです。 安定感とゆったりとした暮らしを想起させるその意匠は、懐かしさと力強さを表現しています。 TX-1 TX-5 TX-6 TX-7 風合いで選ぶレンガタイル ― 当社のこだわり 当社では、レンガの自然な焼きムラや成型の個性を大切にしつつ、本レンガの表情を忠実に再現しています。用途や仕上がりイメージに応じて、手押し・ワイヤーカット・ナイフカットなど、様々な風合いの中から最適なレンガタイルをお選びいただけます。 当社のレンガタイルラインナップ 当社のレンガタイル全製品を一覧ページにてご確認いただけます。詳細ページを経由せず、そのまま簡単にサンプル請求も可能ですので、ぜひご利用ください!
- 施工事例を更新いたしました!ブリックタイルCAN’BRICK「マンチェスター(MC-1)」
株式会社フリークラウド様設計の「suiu」nagano toedaレストラン内装に、ブリックタイルCAN’BRICK 「マンチェスター(MC-1)」 をご採用いただきました。
- 施工事例を更新いたしました!ブリックタイルCAN’BRICK「マンチェスター(MC-1)」
株式会社フリークラウド様設計のオフィス内装に、ブリックタイルCAN’BRICK 「マンチェスター(MC-1)」 をご採用いただきました。
- 施工事例を更新いたしました!白いレンガタイルを使用したオフィス。
株式会社エンティオス様設計のオフィス内装に、ブリックタイルCAN’BRICK 「シロブリ(WH-2)」 をご採用いただきました。
- ブリックタイル(レンガタイル)の選び方:理想の空間を実現するためのポイント
はじめに、レンガというマテリアルは歴史的に日本や世界で広く使用されてきました。例えば、日本であると横浜の赤レンガ倉庫が代表的です。そんなレンガの意匠を再現するため、空間を彩るブリックタイルはさまざまな場面で採用されてきました。レンガを積むことができない場面や、積むことによるコスト増を避けるため、壁面に貼ることができるブリックタイルは空間デザインにおいて重宝されています。この記事では、ブリックタイルの選び方をステップごとに説明していきます。 1. はじめに 2. ブリックタイルの種類と特徴 セメント二次製品 スライスレンガ 3. ブリックタイルの形状と色味を選ぶ 赤レンガ系ブリックタイル 茶色系ブリックタイル 黒レンガ系ブリックタイル 白レンガ系ブリックタイル 4. ブリックタイルの貼り方のデザインの工夫 馬踏み目地 イギリス張り フランス張り イングリッシュガーデン張り アメリカ張り ランダム張り 5. ブリックタイルの購入ガイド 信頼できるメーカーとブランドの紹介 購入先の選び方と注意点 オンラインストア vs メーカー直販 サンプルの取り寄せ 1. ブリックタイルの種類と特徴 セメント二次製品 セメント二次製品のブリックタイルは、レンガの表面の意匠を再現したセメント加工品のタイルです。このタイプのブリックタイルは、以下のような特徴があります。 軽量: セメントを使用することで、本物のレンガよりも軽量に仕上がり、建物への負担を軽減します。 耐久性: セメントの特性により、耐久性が高く、外壁や高湿度の場所にも適しています。 コストパフォーマンス: 製造コストが比較的低く、経済的に優れた選択肢となります。装飾性と機能性を兼ね備えた素材として人気があります。 デザインの多様性: セメントを使用することで、さまざまなデザインや色のバリエーションが可能です。どんなインテリアスタイルにもマッチするデザインを選ぶことができます。レンガ同様、経年変化によって味わい深くなります。時間とともに変化する美しさを楽しむことができます。 スライスレンガ スライスレンガは、本物のレンガを薄くスライスしたタイルで、以下のような特徴があります。 本物の質感: 本レンガを使用するため、自然な質感や色合いを持ち、本物のレンガ壁のような風合いを楽しむことができます。ヴィンテージ感やクラシックな雰囲気を求める場合に最適です。 厚み: スライスレンガは厚みが比較的薄いため、スペースを有効に活用できます。狭い空間でもレンガの風合いを取り入れることができます。 耐火性: 本物のレンガの一部を使用しているため、耐火性に優れています。暖炉の周りやキッチンのバックスプラッシュなど、熱に晒される場所にも適しています。 自然な色合い: スライスレンガは自然な色合いを持つため、経年変化によってさらに味わい深くなります。時間とともに変化する美しさを楽しむことができます。 2. ブリックタイルの形状と色味を選ぶ 一口にブリックタイルと言っても、実はたくさんの種類と形状があります。原産国の違いで色味や製法が異なるため、それによって表面の表情も異なってくるのです。ここではいくつかのタイプのブリックタイルを紹介します。 赤レンガ系 ブリックタイル ENGLAND (ENG-1) 茶色系ブリックタイル CAMBRIDGE (CB-2) 黒レンガ系ブリックタイル KURO BRI(BK-1) 白レンガ系ブリックタイル SHIRO BRI(WH-3) ENG-1 クラシックで温かみのある赤レンガ。伝統的な雰囲気を持ち、どんな空間にも馴染む万能なデザインです。 CB-2 店舗の内装や外壁、書斎など BK-1 モ ダンなオフィスや店舗のファサード、リビングルームのアクセントとして。 WH-3 リビングルームやキッチン、バスルームなど、どんな空間にもマッチします。 3. ブリックタイルの貼り方のデザインの工夫 ブリックタイルの貼り方を工夫することで、同じタイルでも全く異なる印象を与えることができます。デザインの多様性を活かし、空間に独自のスタイルを加えるための貼り方のパターンを紹介します。 貼り方のパターンの多様性 1. 馬踏み目地 • 特徴 : 各段のタイルが半分ずつずれて配置されるパターン。最も一般的な貼り方です。 • 効果 : 安定感とクラシックな雰囲気を与え、どんな空間にも調和します。耐久性も高く、外壁や内装のどちらにも適しています。 2. イギリス張り • 特徴 : 一列ごとに長短のタイルを交互に配置するパターン。長いタイルと短いタイルを組み合わせて貼 ります。 • 効果 : 視覚的にリズミカルで動きのあるデザイン。伝統的なブリックタイルの外観を保ちながら、モダンなインテリアにも適しています。 3. フランス張り • 特徴 : 長いタイルと短いタイルを交互に並べ、一列ごとに配置を変えるパターン。 • 効果 : エレガントで上品なデザインを演出。フランス風のカフェやレストランの内装にぴったりです。 4. イングリッシュガーデン張り • 特徴 : 各段のタイルがランダムに配置され、自然な見た目を重視したパターン。 • 効果 : カジュアルでリラックスした雰囲気を作り出し、庭やテラスなどのアウトドアスペースに最適です。 5. アメリカ張り • 特徴 : 各段のタイルが4分の1ずつずれて配置されるパターン。馬踏み目地の変形です。 • 効果 : 伝統的な雰囲気を保ちながら、モダンなインテリアにも調和します。リビングルームやダイニングルームなど、広い空間に適しています。 6. ランダム張り • 特徴 : タイルをランダムに配置し、自然な見た目を重視したパターン。 • 効果 : 自然な風合いと独自性を持ち、カジュアルでアート感のある空間を演出します。インテリアのアクセントウォールに最適です。 4. ブリックタイルの購入ガイド ブリックタイルの購入にあたっては、信頼できるメーカーやブランドを選ぶことが重要です。ここでは、購入先の選び方や注意点、サンプルの取り寄せについて説明します。特に、 キャン’エンタープライゼズのキャン’ブリック をお勧めします。 メーカーとブランド ブリックタイルの品質は、メーカーやブランドによって大きく異なります。信頼できるメーカーを選ぶことで、耐久性やデザイン性に優れたタイルを手に入れることができます。 キャン’エンタープライゼズのキャン’ブリック • 特徴 : キャン’エンタープライゼズは、高品質のブリックタイルを提供する信頼性の高いメーカーです。豊富なデザインバリエーションと優れた耐久性が特徴です。 • 推奨理由 : 国内生産の安定供給と厳格な品質管理により高強度のタイル。また、環境に配慮した素材を使用している点も魅力です。 購入先の選び方と注意点 ブリックタイルを購入する際には、以下のポイントに注意してください。 • 信頼できる店舗を選ぶ : 実績のある店舗やメーカー直営店から購入することで、品質保証やアフターサポートを受けられます。 • レビューや評価を確認する : 他の購入者のレビューや評価を確認することで、信頼性や品質を事前に把握できます。 オンラインストア vs メーカー直販 それぞれの購入方法にはメリットとデメリットがあります。 オンラインストア メリット : 自宅から簡単に注文でき、豊富な種類を比較できます。価格も比較的安いことが多いです。 デメリット : 実物を確認できないため、色合いや質感が写真と異なる場合があります。また、施工の相談や他に必要なもののアドバイスが得られないことが多いです。 メーカー直販 メリット : 実際に商品サンプルなどを手に取って確認でき、専門スタッフのアドバイスを受けられます。施工の相談や、必要な工具や材料のアドバイスも直接得られます。 サンプルの取り寄せ ブリックタイルを購入する前に、サンプルを取り寄せることをお勧めします。 購入前に試すことの重要性 : 実際の色合いや質感を確認することで、完成後のイメージを具体化できます。 実際の色合いや質感を確認する方法 : サンプルを実際の設置場所に置いて、照明や周囲のインテリアとの相性をチェックしましょう。 ブリックタイルの購入は、信頼できるメーカーや適切な購入先を選ぶことが成功の鍵です。 キャン’エンタープライゼズのキャン’ブリック は、品質とデザイン性に優れた選択肢としておすすめです。ぜひサンプルを取り寄せ、理想の空間作りをお楽しみください。
- ブリックタイルの開口部(窓や玄関)デザイン
ブリックタイルは、その独特の風合いと耐久性から、多くの住宅や商業施設で人気があります。特に窓周りやドア周りなどの開口部に正しくブリックタイルを使用することで、建物のデザインに深みと魅力を加えることができます。この記事では、ブリックタイルを用いた開口部デザインのポイントと事例を紹介します。 フラットアーチ + キーストーンの施工事例 開口部のデザインは住宅の化粧 開口部は住宅の「化粧」とも言える要素です。 たとえば、ジョージアン様式の家では、窓や玄関には装飾的なキーストーンやペディメントが遇らわれることが一般的です。これらの要素は、家全体に洗練されたクラシカルな美しさをもたらします。 細かい部分ですが、"本当にレンガを積んだ家"を再現するには外せないポイントとなります。 今ではタイルを張ることでレンガ積みの意匠を持った家は造ることができるので、”レンガを本当に積んでいたら “と本来あるべき概念を無視している事例が多くみられます。しかし、 本来の積み方のルールを押さえておくことで誰が見ても美しい、構造的にも正しい仕上がりにすることができます。 NGなデザイン(簡易版) レンガ張りのデザインの中でも、しばしば間違えられることの多いデザインをふたつ(簡易版を)紹介します。よく見るデザインなので、何がおかしいのか疑問に感じるかも知れません。重要なポイントは「構造として成立しているか」を考えることです。仮に、窓枠が入っていないと仮定した場合、上のレンガが落ちてきそうかどうか。下図の場合だとどちらも構造的に不安定なものとなっているのがわかると思います。 アーチやリンテル(マグサ)を使わずに窓枠の上部にタイルを横断するように設置しない。 縦積みを使用しているが、開口部より小さいレンガのリンテル(マグサ)は使わない。 GOODなデザイン(簡易版) 上記での部分を踏まえて、ここでは上部のマグササイズを変更することにより、バランスの取れた構造美を実現しています。 フラットアーチ 開口部より1~2 個はみ出させる形で縦積みを使用することで、上部の荷重を支えられるリンテルデザインを作ることができる。 かっこいいブリックタイル張りデザイン(玄人版) 上記の簡易版ではよく見る開口部デザインの正しい貼り方を紹介しました。ここではより、凝った方のための玄人版レンガデザインについて紹介していきます。 セグメンタルアーチ セグメンタルアーチ + キーストーン フラットアーチ + ブルズアイ セグメンタルアーチ:定型化(形が揃えられていない)されていないレンガと扇形の目地が特徴。アーチの両端での接続部分の角度が72° であることが好ましい。 この角度は、アーチの形状が美しく見えるだけでなく、構造的な安定性や荷重分散にも寄与する。 アーチのスパン(水平方向の長さ)が1 フィート増えるごとに、アーチが上昇する高さは最大2.54cm増加します。これは、アーチの形状や傾斜を示す指標として使用される。 セグメンタルアーチに キーストーン (要石)* が付くタイプ:上部にキーストーンを設置することで、窓にデザイン的なアクセントをつけることが可能。 キーストーン の適切なサイズは、水平方向の高さがブリック4 段分と目地3 段分を合わせたものであることが望ましいとされています。 フラットアーチとブルズアイ:フラットアーチの端に ブルズアイ を設置するスタイル。ニューイングランドの建物で稀に見られるデザイン。 *キーストーン(要石)とは?? 組積造の建築物における、アーチの頂上部分を示す石材を「キーストーン」と呼びます。本来は周囲の建材が崩れないように締める役目を持つ、構造的にも重要なものです。弊社のキーストーンはブリックタイル キャン’ブリックと同じく”貼るキーストーン”です。本レンガを積んだような、本格的な意匠を再現したい場合に最適なハイセンスなアイテム。 ブリックタイル + ブルズアイ ブリックタイルと合わせるアクセントタイル 上記で紹介したようなアイテムはかなり使用すること自体"ツウ"なので、知られておりませんが、当社では、多くのアクセサリたちを取り揃えています。 ブリックタイルのデザイン張り施工はキャン'エンタープライゼズへ! 細かいポイントを押さえておくことで、レンガの意匠をより本格的に魅せることができます。貴方の空間イメージをより確実に形にするために、お困りの際は当社までお問い合わせください!